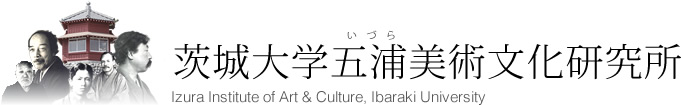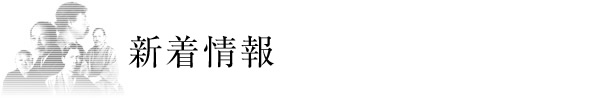開校当初に定められた東京美術学校校服は、奈良朝の服装に倣ったもので、世間の注目をあつめた。生徒は入学後1ヶ月以内に、自費で校服を作って着用することを定められていたが、服装の形や色などについてはどのように規定があったのか判然としない。明治22年4月15日発行の「美術」第3号には「教員のハ茶色の綾毛織地に水色甲斐絹の裏を附け生徒ハ鉄色無地の毛織に水色の裏を附け帽子も無類異形の物なれば其圖を上に掲ぐ」とあり、生徒用の服の記述は、武山着用の服にほぼ符合している。図では腋下が全部開いているが、武山着用は裾から35センチまでが開いている。 この校服は明治30年からは儀式用となり、ふだんは、略式の襷をつけることとなった。